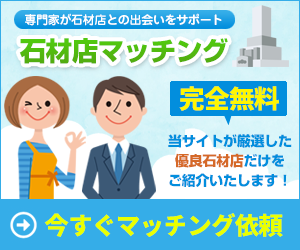今、お墓を継いでくれる人がいない、子供や孫の負担をなくしたい、という理由から、墓じまいをする人が急増しています。
墓じまいとは、お墓の継承者がいなくても困らないように先祖代々の現墓地を片付けることですが、その墓じまい後の選択肢として最も注目されているのが「永代供養(えいたいくよう)」です。
最近メディアで取り上げられることも多く「永代供養」という言葉を知っている方も大勢いらっしゃると思います。
しかし、具体的にどんなお供養なのかはご存知でしょうか?
従来のお墓と何が違って、費用はどれくらいかかるのか、また、どんな行政手続きが必要か。
今回は、そういった疑問にお答えしていきたいと思います。実際に永代供養をお考えの方、必見です。どうぞご参考ください。
永代供養の特徴と費用

永代供養とは、どんなお供養なのでしょうか?
永代とは何を意味するのでしょうか?
まずは、永代供養の特徴や、従来のお墓との違い、費用の相場についてご説明したいと思います。
永代供養とは
永代供養とは、霊園や寺院が遺族に代わって、遺骨の管理や供養をしてくれる契約のことです。
永代というのは、霊園や寺院が存続する限りずっと、という意味です。
ただし、ずっと〝個別に〟供養されるということではありません。
従来のお墓が、継承者がいる限り子孫代々受け継がれていくのに対し、永代供養は、初めから他の遺骨と合同埋葬されるか、初めに個別納骨されても、十七回忌や三十三回忌、五十回忌などで切り上げて合同埋葬されるのが一般的です。
また、納める遺骨についても、夫婦単位や二世代までというように限定されるケースがほとんどです。
【関連記事】永代供養の相場は?お寺の宗派や埋葬方法の違いによる注意点
【関連記事】永代供養墓は無縁仏対策に最適
永代供養の費用
永代供養は、大体の場合、初めに永代供養料を支払ってしまえば、年間費用など、その他の支払いは基本的には不要です。
永代供養料の相場は30~150万円程度で、埋葬方法や個別供養の年数によって大幅に異なります。
従来のお墓は、永代使用料や墓石代、工事費などがかかり、相場は200~300万円程度で、墓地の立地や広さ、使用する石などによって費用が上下します。
それに加え、墓地を維持するための年間管理料が、毎年一定額必要です。
年間管理料の相場は、公営の場合は数千円程度、民間や寺院の場合は5千~2万円程度です。
ちなみに「永代使用料」という言葉が「永代供養」と混同されがちですが、「永代使用料」とは、墓地を代々使用する権利の購入費のことで、これを初めに支払っておけば、年間費用など維持費を支払うだけで、子孫代々使用していくことができるのです。
永代供養の種類とそれぞれの費用

では、永代供養の具体的な納骨・埋葬方法について詳しく見ていきましょう。
永代供養のスタイルは、墓所によって異なりますが、大きく分けると、単独や夫婦単位で納骨される「個別納骨型」と、他の遺骨と合同埋葬される「合祀(ごうし)型」になります。
こちらでは、個別納骨型と合祀型という観点から、永代供養の実態や費用についてふれていきたいと思います。
個別納骨型の永代供養墓

個別納骨には、従来のお墓と変わらない個々の墓石があるタイプや、納骨堂でみられる仏壇の下段に遺骨を納める霊廟型とよばれるタイプなど、その場所を占有できる「独立形式」と、納骨場所が細かく区切られた段型墓地や、ロッカー式の納骨堂など、区切られた空間を使用できる「集団形式」があります。
住宅でいえば一戸建ての家とマンションのような違いです。独立形式の相場は60~150万円程度、集団形式の相場は、20~100万円程度となります。
また、個別型の永代供養で大きな問題となるのが、「個別供養の期間」です。
多くの場合、十七回忌、三十三回忌、五十回忌などを目安に個別供養を終了し、合同埋葬へと移行されますが、中には、無期限に個別供養をしてくれる場合もあります。
そういった個別供養の期間によっても費用が上下します。
その他にも、一霊のみ、夫婦のみといった収納遺骨の制限や、占有スペースの広さ、立地などによって、価格が変動します。
合祀(合葬)型の永代供養墓

他の遺骨と一緒に合同埋葬するスタイルです。
埋葬場所に供養塔やモニュメントなどが建てられたり、参拝スペースがあったりして、そこでお参りすることができます。
こういった合祀型の相場は10~30万円程度ですが、一霊につき1~3万円程度という非常に安価な費用で受け入れてくれる墓所もあります。
また、故人の名前や没日、没年齢などの彫刻プレートを作成できるなど、その墓所によって異なったサービスがあります。
【関連記事】合葬墓とは?公営と民営の費用相場から納骨堂との違いも解説
永代供養の手続き

では、現墓地の墓じまいをして永代供養の墓所へと移行するために必要な行政手続きについて見ていきましょう。
また、ご自身の終活として、永代供養を生前予約しておくための手続きについてもご紹介します。
墓じまいなど改葬する場合の行政手続き
永代供養を依頼する改葬先の墓所が決まったら、現在の墓所から遺骨を移すための行政手続きが必要です。
- 改葬先の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
- 現墓所の管理者に「埋葬証明書」または「納骨証明書」を発行してもらいます。
- 現墓所のある市区町村役所の窓口またはホームページから「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。複数のお骨を改葬する場合は、各市区町村の指示に従って複数用の書類を使用、添付するなどします。
- 現墓所のある市区町村役所の窓口にて「受入証明書」「埋葬証明書(納骨証明書)」「改葬許可申請書」を提出します。この際に、申請者の印鑑も必要です。
※改葬許可申請者と墓地使用者が異なる場合は「承諾書」が必要です。
※改葬許可申請者と別の人が手続きを行う場合は「委任状」が必要です。
- 改葬の申請を行うと「改葬許可書」が発行されます。
「改葬許可書」は一遺骨に1枚が必要ですので、申請の際に注意してください。
- 改葬先の管理者に「改葬許可書」を提出します。
【関連記事】『改葬』意味は?増加の理由と必要な費用|お墓の引越し手順
生前に永代供養を申し込む場合
多くの寺院や民営の霊園で、永代供養の生前申し込みをすることができます。
寺院や霊園と契約し、費用を支払えば契約完了となります。
申し込みの際には、住民票などの身分を証明するものや、親族などの連絡先、その連絡者の署名、押印が必要になることがあります。契約が完了すると、「永代供養墓使用承諾書」といったものが発行されます。
この書類は、納骨の際に必要になりますので、しっかり保管しておくことが大事です。
これより後の手続きは、残される家族に託すことになりますので、承諾書の保管場所が家族に伝わるようにしておかなくてはいけません。
もちろん、永代供養を申し込みたいとう意向についてもしっかり伝えておきましょう。
まとめ
永代供養は、霊園や寺院に遺骨の供養を任せられる安心のお供養です。
費用や納骨方法も多様で、予算や立地、個別納骨期間など、希望にあった供養の形を選択することができるでしょう。
とりわけ、墓じまいを検討されている方にとっては、永代供養は合理的な供養方法といえます。
現墓地を片付けて永代供養先へ改葬する場合、書類手続きに手間がかかりますが、順を追っていけば難しい手続きではありませんし、最近は手続き代行をしてくれる業者もありますので、そちらに依頼してもよいでしょう。
「墓じまいは何回忌ですれば良いの?」と墓じまいの時期を気にされる方も多いと思いますが、墓じまいをする時期に決まりはありません。
思い立ち、ご家族で意見がまとまった時が墓じまいに適した時期と言えます。
自分たち家族にあった永代供養先を見つけ、家族や親族と十分話し合いながら墓じまいの手続きを進めていくようにしましょう。
優良石材店無料マッチング依頼
【関連記事】
・墓じまい|トラブル回避のポイントと手続き代行可能な業者選び
・墓じまいの意味とは?撤去と供養の気になる費用と8つの手順
・檀家をやめたいと思ったら|菩提寺のメリットと離檀によるデメリット
・墓じまい後の遺骨はどうする?
・無縁墓にならないために家族でできること!生前にできる対策
墓じまいカテゴリーページに戻る