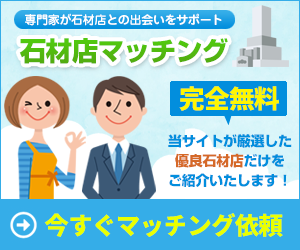現在では渡すところも少しずつ少なくなってきましたが、現在でも、葬儀(お葬式)の際に「お清めの塩を持って帰ってもらう」という風習は息づいています。
この「お清めの塩」は香典返しについていることもありますが、「葬儀から帰った父に、母がお清めの塩を振っていたのを覚えている」というように家庭で用意することもあります。
では、この「お清めの塩」にはどのような意味があるのでしょうか?
また、余った塩などはどのように処分するべきなのでしょうか?
目次
お清めの塩の意味はもともと「穢れを払うためのもの」

お清めの塩は、もともとは神道の考え方によって利用されるようになったものでした。
神道では、死を「穢れ(けがれ)」ととらえます。この「穢れ」とは「汚れ」とは意味が異なります。
「汚いもの」ではなくて、「生命力が枯れること(気枯れ)」に由来している言葉だともいわれており、これをはらう必要があると考えられているのです。
そして塩は、その穢れをはらうためのものとして神聖化されていました。
もともとは神道の考え方であったお清めの塩ですが、仏式の葬儀の香典返しにもお清めの塩がつけられている場合があります。
つまり、この点では仏式と神式が混在していると考えることができます。
この理由は定かではありませんが、かつては神道と仏教が一体化していたという理由もあるのかもしれません。
現在、葬儀の際に配られるお清めの塩の意味は、穢れを払うためのものであると言えます。
お清めの塩、使い忘れた場合はどうする?

お清めの塩は、胸に振りかけてから背中に振り、最後に足元に振りかけて使います。
玄関前で塩を振り、それを一度踏んでから家の中に入るのが一般的です。
もちろん人にやってもらうのでも構いません(※地域などによって多少の違いがある場合もあります)。
では、お清めの塩を使い忘れた場合はどうすればよいのでしょうか。
上でも述べた通り、お清めの塩はもともと神道の考え方に基づく風習です。
そのため、仏教の葬儀やキリスト教の葬儀の場合は、そもそもお清めの塩を使わなくても構いません。
仏教やキリスト教の葬儀においてお清めの塩が配られた場合は、宗教的な意味が含まれているというよりは、「風習」「習慣」によるものだと理解しておく方がよいでしょう。
また、神式の葬儀においても、現在ではお清めの塩を使わないところも増えてきました。
お清めの塩は火葬場から戻ってきたときにも使われるものですが、葬儀会社であってすら、「お清めの塩は使わない」としているところもありました。
この葬儀会社の場合は、「おしぼりを渡して手を清めてもらうので、お清めの塩は使わない」というスタイルをとっていました(もちろん、同じ地域でもお清めの塩を使う葬儀会社もあります)。
香典返しに入れる塩に関しても、「喪家側から希望があれば小袋をつけるが、希望がない限りはつけない(=つけないのがスタンダードスタイル)」としている場合も多くあります。
宗教を重んじる人が少なくなっていること、小さな葬儀が主流になっていることもあり、お清めの塩はそれほど重要視されるものではなくなってきたのかもしれません。
このため、本人が気にしないのであれば、お清めの塩を使い忘れても何の問題もありません。
「気になる」という場合は、喪服を着た状態で一度外に出て、お清めの塩を振ってから家の中に入りなおせばよいでしょう。
余ったお清めの塩はどうすればいいの?
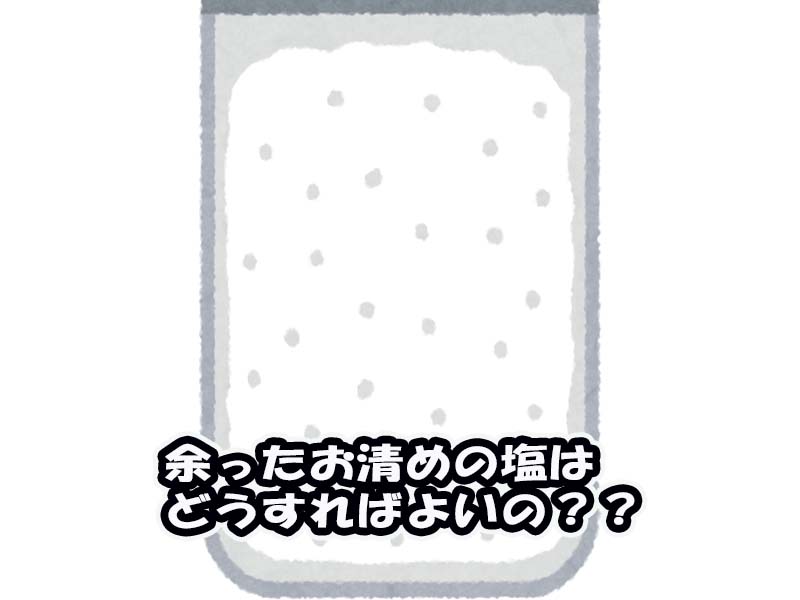
お清めの塩は、それほど多く使うものではありません。そのため、基本的には余ってしまうものです。
では、余ったお清めの塩はどうすればよいのでしょうか?
余ったお清めの塩は、そのまま捨ててしまって構いません。
お清めの塩はたしかに死の穢れを清める効果が期待できるものですが、お清めの塩自体に神様などが宿っているわけではありません。そのため一般ごみとして捨ててしまっても何の問題もありません。
ただ、「葬儀にかかわるものをそのまま捨ててしまうのは、どうにも抵抗がある」という人もいるでしょう。
そのような場合は庭の土に撒いたり、殺菌用の塩として使ったりするとよいでしょう。また、水に流して処分しても問題ありません。
なお、お清めの塩は料理に使ってはいけません。
これは宗教的な理由というよりも、お清めの塩の加工方法にあります。
お清めの塩は、固まることを防止するために、乾燥剤などを入れていることがあります。
そのため食用には適さないことが多いのです。
このような知識が広まっていなかった時代は食用に使うご家庭もありましたが、避けるようにしてください。
葬儀のお清めの塩についてまとめ
「お清めの塩」は、神道の考え方でありながら、仏教をはじめとしてさまざまな宗教の葬儀において配られるようになったものです。
現在は少しずつ下火になっていっている風習ではありますが、現在もお清めの塩をもらうシチュエーションはあります。
宗教観の薄い人にとってはそれほど重要視するものではありませんし忘れてしまっても問題がないものではありますが、「気になる」という人は使い方などを覚えておきましょう。
関連記事:お通夜に喪服は失礼って本当?葬式の男女別服装と髪型のマナー
関連記事:焼香の回数とやり方は?喪主と参列者で仕方に違いはあるの?
関連記事:香典を後日職場で渡す時の袋の表書きや挨拶と渡し方のマナー
関連記事:通夜・告別式での席順マナー
☆ブログランキング参加中☆
クリックしていただけると励みになります。

通夜と告別式の席順は?親族と参列者でお葬式席順マナー|墓ミカタ
通夜や葬儀(告別式)の場では、喪主を初めとし、近しい親族らはそれぞれ決まった席に着くこととなります。その席順には、「血縁の順がよい」「家族はまとまって座る」など様々な考えがあり、地域やお寺、家の考え方によっても違ってきま […]

キリスト教の葬式に参列する際のマナーは?香典やお悔やみの言葉は?
日本の葬式の9割は仏教式なので、キリスト教の葬式に参列する機会はなかなかないでしょう。しかし、だからこそ、急にキリスト教の葬式に出ることになったら、慌ててしまいます。「お悔やみの言葉にタブーはあるの?」「讃美歌などを歌う […]

神道の葬式に参列する際のマナーを解説!儀式の流れ香典の表書きは?
神道の葬式に参列することになったら、「仏式とはどう違う?」「香典袋は何を選べばいいの?」と慌ててしまう人が多いでしょう。神道の葬式を、神葬祭といいます。神葬祭の流れや参列時のマナーについて解説します。

葬儀のお清めの塩の意味は?使い忘れた時や余った塩はどうすれば?
現在では渡すところも少しずつ少なくなってきましたが、現在でも、葬儀(お葬式)の際に「お清めの塩を持って帰ってもらう」という風習は息づいています。 この「お清めの塩」は香典返しについていることもありますが、「 […]

焼香の回数とやり方は?喪主と参列者で仕方に違いはあるの?
仏教の葬儀では、「焼香」を行う必要があります。 日常的に行うことのない焼香は、いざと言うときに「どうやるだっけ・・」と不安になった方も多いと思います。 今回はこの「焼香」のやり方について取り上 […]