
お墓を建てようと、業者から見積を取り寄せたときの反応といえば、十中八九「・・・高い!」ではないでしょうか。
サンプルの石を見せてもらったとしても、値段の違いが見た目ではわからず、営業マンに言われるまま契約、結果トラブルに発展したという話をよく耳にします。
そこで今回は墓石の種類と選び方をご紹介します。
石材の特徴や、それに関係してくる価格設定の根拠を知ることで、より賢くお墓選びをしましょう。
目次
墓石に使われる石の種類
墓石に使われる石材といえば、白い石を想像されるかと思いますが、その白い石をひとつ取っても産地によって価格と質が大きく変わります。
ここでは、ひとつひとつ石の特徴を見ていきましょう。
お墓に使用される石は大きく分けて4種類あります。
「花崗岩」「安山岩」「斑糲岩(はんれいがん)」「閃緑岩」がそれにあたり、それを細かく種類に分けていくと300種類が墓石に使われます。
しかしながら、現在墓石に使われる石のほとんどが「花崗岩」と「安山岩」なので、今回はその2種類について詳しく説明します。
花崗岩
いわゆる「御影石」と呼ばれる石は花崗岩にあたります。
これらは火山が爆発したときに、地下深いところで冷えて固まってできた岩石です。
墓地でよく見かける白い石がそうです。
硬く、熱などにも強いため、普段風雨にさらされる墓石用としてはもってこいの石材と言えるでしょう。
現在では産出量が多い中国産が8割以上の大きなシェアを占めていますが、希少性や耐久性、見た目の素晴らしさから、日本産の石も高値で販売されています。
主な花崗岩(御影石)
庵治石(香川県)

世界最高峰の高級石材。
粒が細かく、遠目からみると龍のうろこの模様に見え、かの彫刻家イサム・ノグチをも魅了した。
羽黒糠目(茨城県)

庵治石に次ぐ、国産高級石材。
粒が細かいのはもちろんのこと、全体が青みがかって見える。
万成石(岡山県)

全体がピンクがかって見えるため、女性に人気のある石材。
産出量が減少しているため、これまた高級品。
真壁小目(茨城県)

羽黒糠目と同様、茨城県で取れる石。
少し大きめな水晶の結晶が特徴的。
上記の3種類に比べれば比較的安価だが、近年価格は高騰している。
G614(中国)

定番の白御影石。価格も安価なため、石塔だけでなく外柵(墓地のまわりを囲む柵)に使用されることも多い。
G623(中国)

粒が粗く、薄くピンクががかっているのが特徴で外柵に多く使われている。
ファイングレイン(スウェーデン)

世界でも最高級の黒御影石。
細かく目がつまっており、非常に硬い。
また独特の光沢を放つ。
クンナム(インド)

ファイングレインに次ぐクオリティを持つ黒御影石。
ファイングレインが予算的に厳しいときに選ばれることもある。
インパラブルー(南アフリカ)

黒い表面に、青く光る粒があるのが特徴的な黒御影石。
安山岩
花崗岩と異なり、マグマが地表近くや地表へ噴火したあとに冷えて固まった岩石が安山岩です。急速に冷えて固まったせいか、目が非常に細かく灰色をしているのが特徴です。
主な安山岩
本小松石(神奈川県)

神奈川県真鶴産。
庵治石が西の横綱ならば東の横綱と称される高級石材。江戸城の建築で使われたことで、徳川将軍家代々の建墓にも採用されている。
独特の緑がかった見た目が大きな特徴。
蛇足ですが、よく大理石は墓石に使えないのかと聞かれるのですが、耐久性に難があるのでほとんど使われることはありません。
墓石の選び方3つのポイント
さて、墓石に使われるおもな石の種類だけでもこれだけ多くある中で注目すべき点は何なのか?
おもに3点あります。
① 墓石の色
一般的にお墓は関東から西は白御影、東は黒御影で建てられることが多いと言われています。
それは東北地方では黒御影石が多く産出されたことが大きな理由です。
ただ近年、石材は輸入に頼っていることもあるため、個々人の好みで選ばれることが多いです。
② 墓石の硬さ
何度も建て替えるものではありませんので、石の頑丈さにもこだわりたいポイントです。
目が細かくつまっている石ほど硬度が高く、価格も高いといわれており(ただし日本産の希少な石材はこの限りではありません)、硬さだけで言うならば黒御影石は間違いのない選択と言えるでしょう。
実際私も石材店の営業現場でも、頑丈さ重視のお客様には多少予算が上回っても、黒御影石をおすすめしていたほどです。
③ 墓石の吸水率
石の表面は、スポンジのように目に見えない細かな無数の穴があいているため、地面から水分を吸い上げ、雨やお参りの掃除の際の水を吸う特性があります。
白御影石が普段よりも濃い色に変色しているところをご覧になったことがある方がいらっしゃると思いますが、その原因は水を吸ってしまったことによります。
乾けば元に戻りますが、この繰り返しが、長い年月をかけて墓石を風化させる原因とみられています。
目が粗い石ほど水が吸いやすいため、一般的に耐久性に難があるといわれます。
墓石の価格は何で決まるのか?
お墓の購入費用の全国平均は約200万円です。
そのうち、墓地代にあたる永代使用料の平均額が約60万円と言われていますので、墓石の平均的な価格は140万円程度であると考えられます。
前述の石選びの注目点を踏まえると、墓石の値段は上記でご紹介した『色』『硬さ』『吸水率』の3点で決まる印象を与えてしまいますが、必ずしもそうではありません。
日本産墓石材は、スペック以上に高価なものがほとんどです。
石の価格そのものだけでなく、加工費や人件費の高騰の影響を受けているからです。
例えば「石のダイアモンド」とも例えられる、香川県産の庵治石や東の横綱・本小松石と中国産のG623を同じ分量だけ使ってお墓を建てた場合、金額がひと桁違うほどです。
そのため、庵治石や本小松石などの銘石といわれる石材でお墓を建てられる方は、政治家や実業家などの資産家が多くを占めます。
ただ墓石に限らず、日本産が良くて外国産が悪いと考えてしまいがちですが、必ずしもそうではありません。
中国での加工技術は一昔前よりずっと向上していますし、スウェーデン産の黒御影石ファイングレインの品質は世界トップクラスを誇ります。
今後ますます外国産石材の支持が高まっていくことでしょう。
【関連記事】中国産墓石はダメ?国産材と値段など違いを比較し上手に選ぶ
また、墓石業界では他言はタブーとされていますが、墓石は地域による価格差も非常に大きいです。
都市部と地方では、同じ石種で同じデザインで墓石を建てても金額に大きな開きがある場合が多いです。
都会は田舎と比較して、永代使用料だけではなく墓石の価格も高いです。
墓石を相場より安い値段で建てる方法
高額な墓石(お墓)をできる限り安く建てたいと思うのは当然のこと。条件はありますが、お墓を相場より安い値段で建てる方法はあります。
墓石を相場よりも安く建てる条件は『公営墓地』または『共同墓地』であることです。
民営霊園の場合は指定石材店間で値引き競争にならない様な仕組みになっている可能性が高いです。また、寺院墓地の場合は、民営霊園と同様に競争がおこらない仕組みになっている場合や指定石材店が一社で言い値のため近隣の相場よりも高くなる可能性もあります。
しかし、公営墓地や共同墓地であれば指定石材店がいないため、近隣の相場よりも安く建てられる可能性があります。
関連記事:東京都立霊園について
公営墓地または共同墓地でお墓を安く建てるポイントは石材店2~3社から相見積もりをとることです。それによって石材店間の競争が生まれ、近隣の相場よりもお墓(墓石)を安く建てる事が可能です。
お墓探しのミカタの石材店無料マッチングは、公営墓地や共同墓地で石材店探しの際に便利です。
墓石の産地偽装の問題
産地偽装の問題は、墓石も無縁ではありません。
産地によって大きく値段が変わり、かつ素人では石の種類を判別しづらいだけに、残念ながらそれを行っている業者も存在します。
現在、一般社団法人「日本石材産業協会」では、石材産地証明書(国産・外国産ともに)、また「全国優良石材店の会(全優石)」の認定店では全優石による保証書の発行しており、産地偽装防止に努めています。
墓石の選び方まとめ
以上をまとめると、石の産地、希少性、産出量、丈夫さ(硬度)で値段が変動してくることがわかります。
もちろん、リーズナブルで耐久性のある石材も多くありますが、銘石と呼ばれる石の独特の存在感は値段に代えられないものでしょう。
しかし、無理して身の丈以上のお墓を建てたことにより、残された家族のその後の生活が苦しくなっては本末転倒。
お財布と相談しながら後悔のない墓石選びをしたいものです。
【関連記事】墓石を最安の値段で建てる3つの墓地タイプ別のコツ
【関連記事】お墓の基礎工事の施工工程と価格相場|墓石工事の基礎知識
【関連記事】お墓はローンで購入可能?銀行と信販会社の審査と金利を比較
【関連記事】お墓のリフォームの時期と費用について
【関連記事】お墓の値段と費用相場|永代使用料、墓石代、墓地管理費

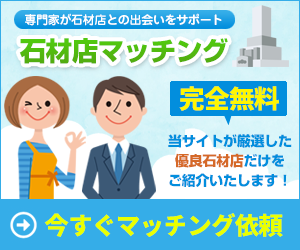

コメント